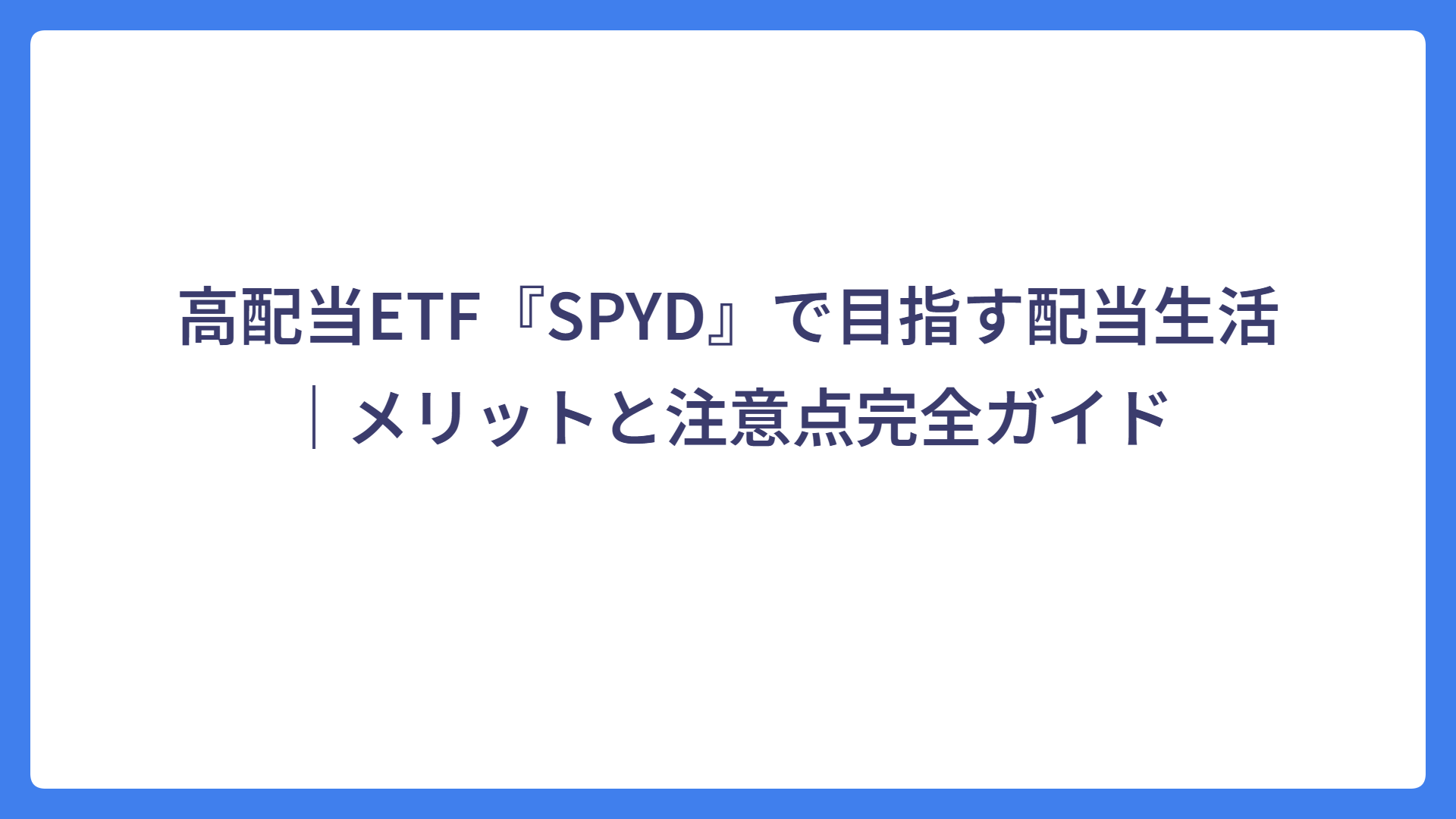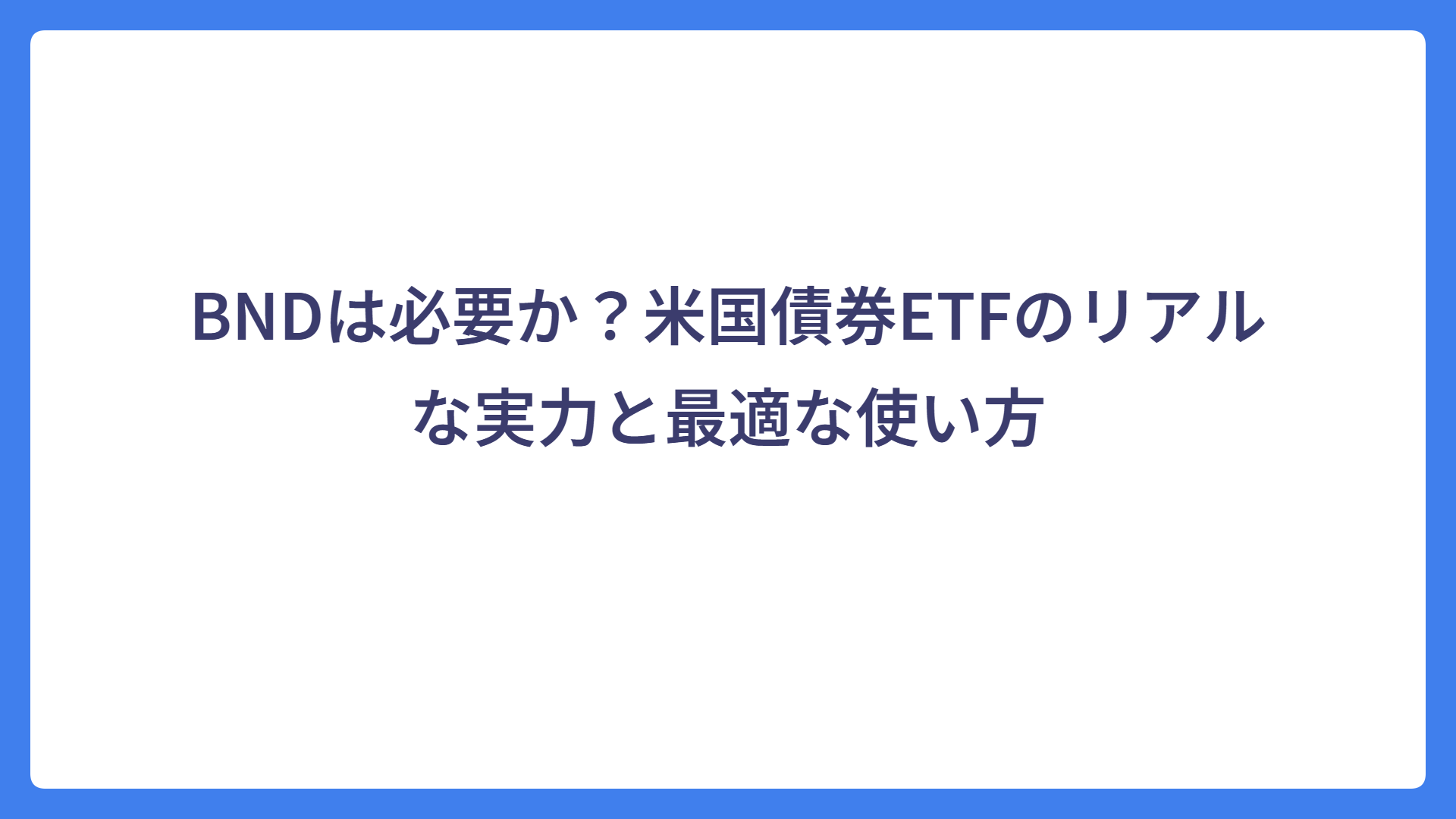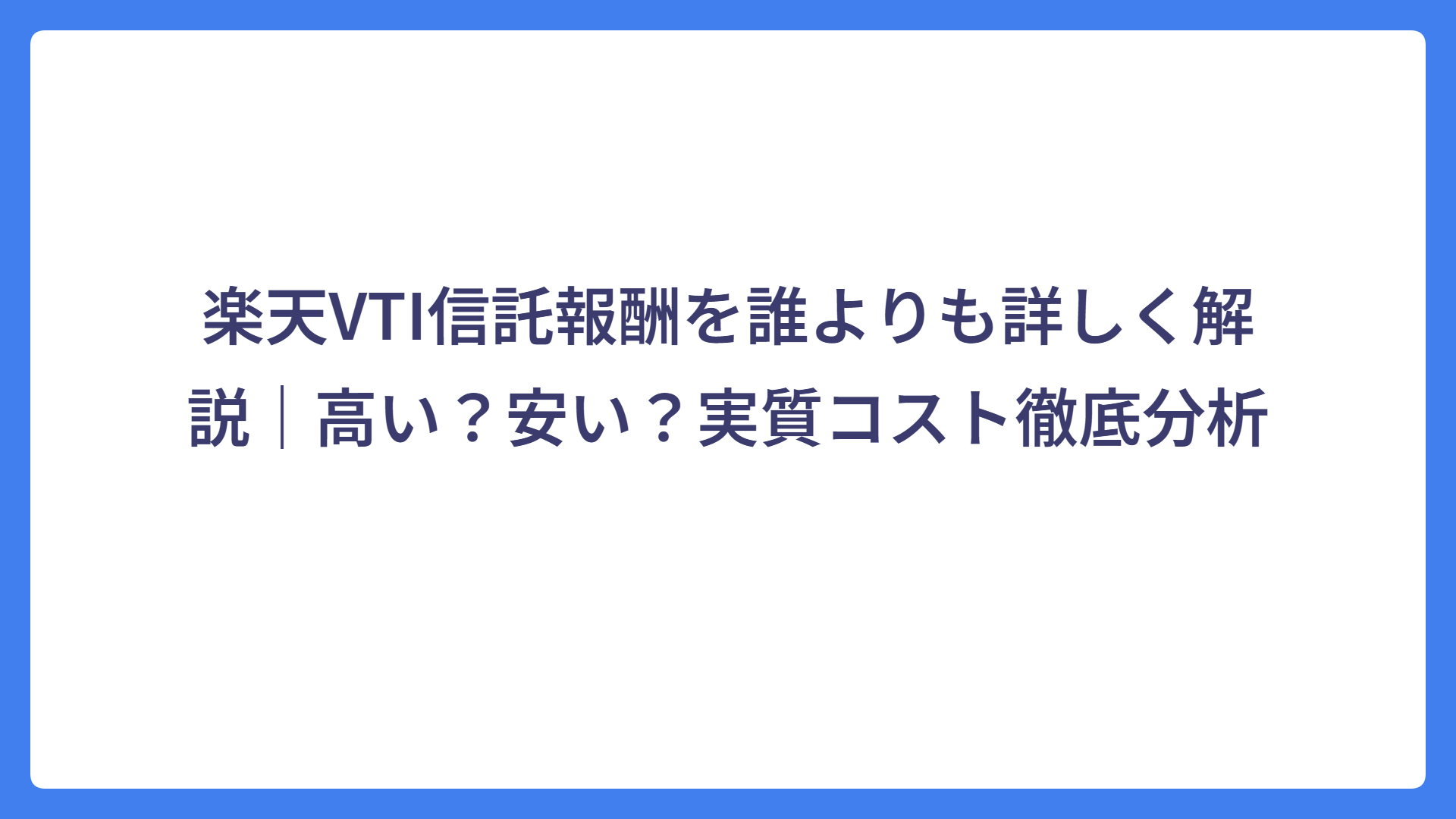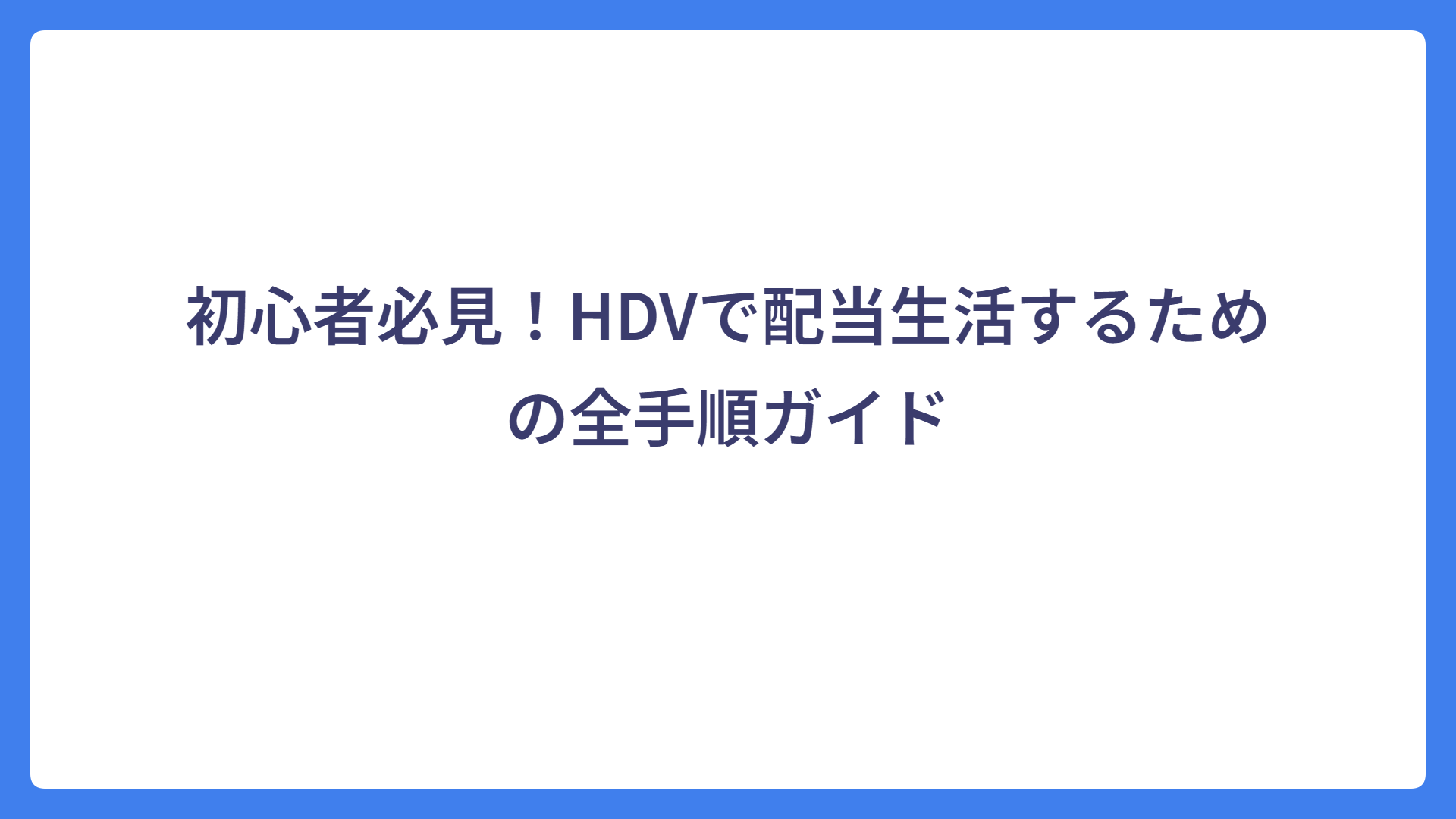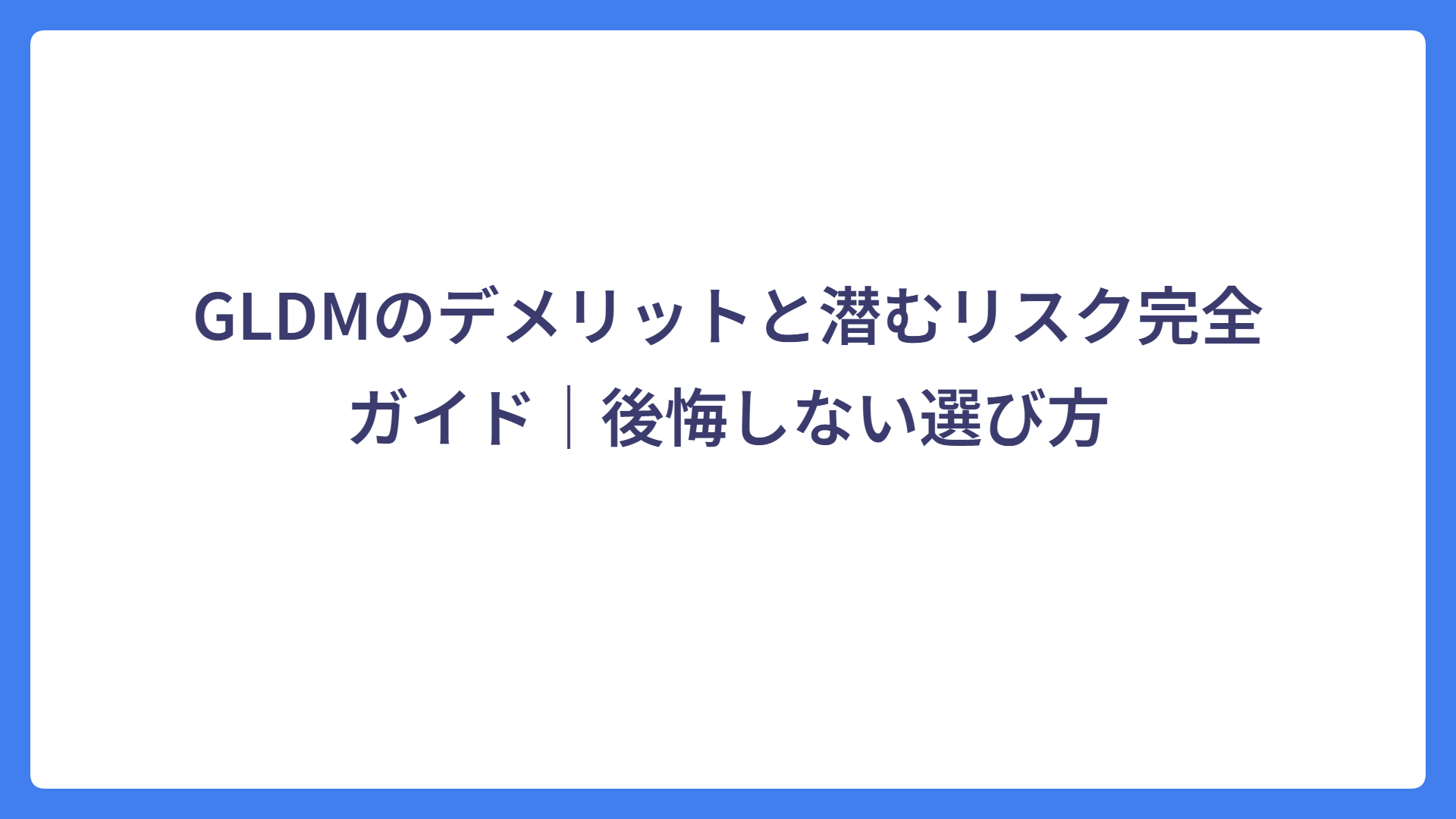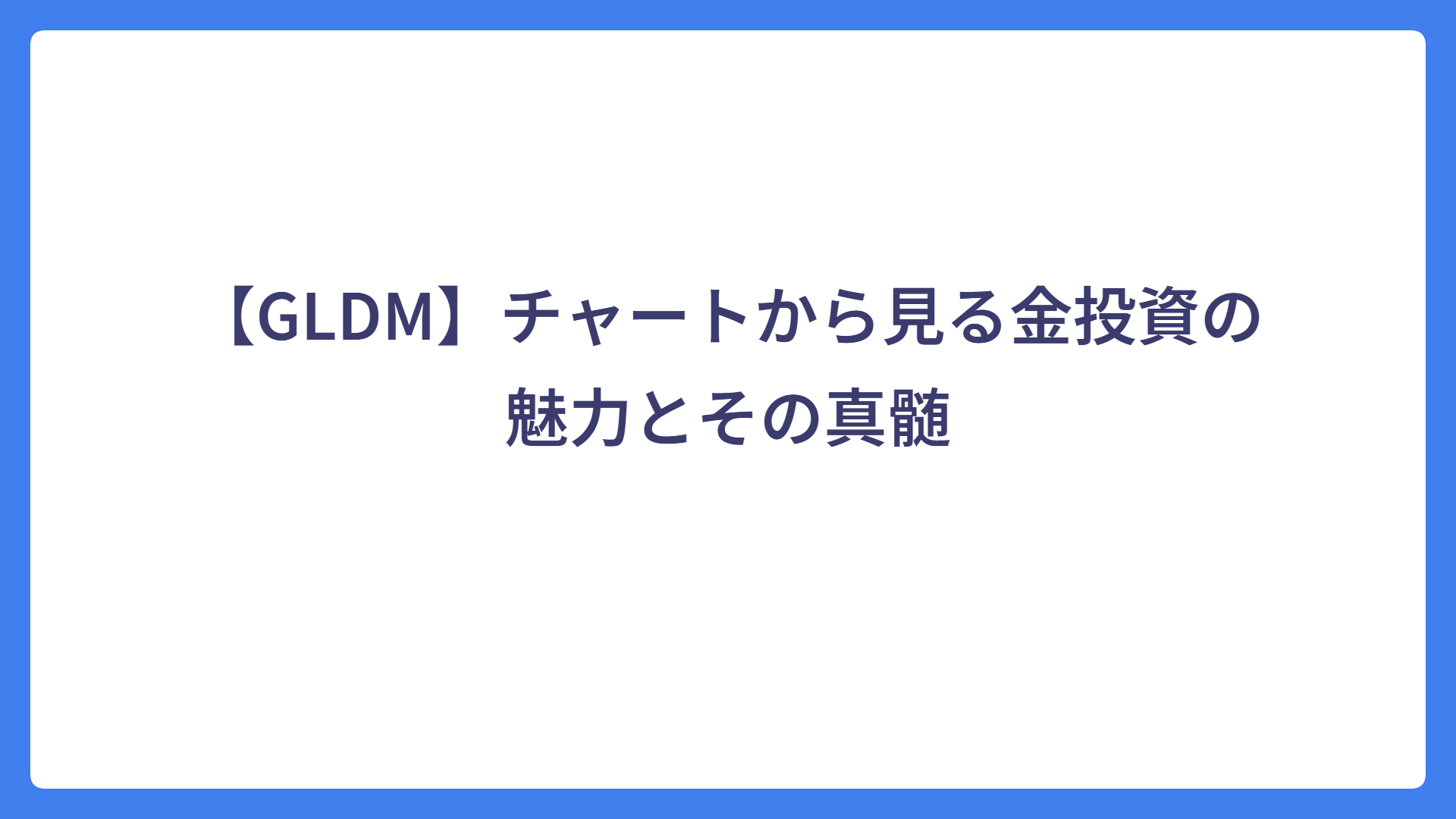【EDV vs TLT】 値動き・利回り徹底比較&賢い選び方
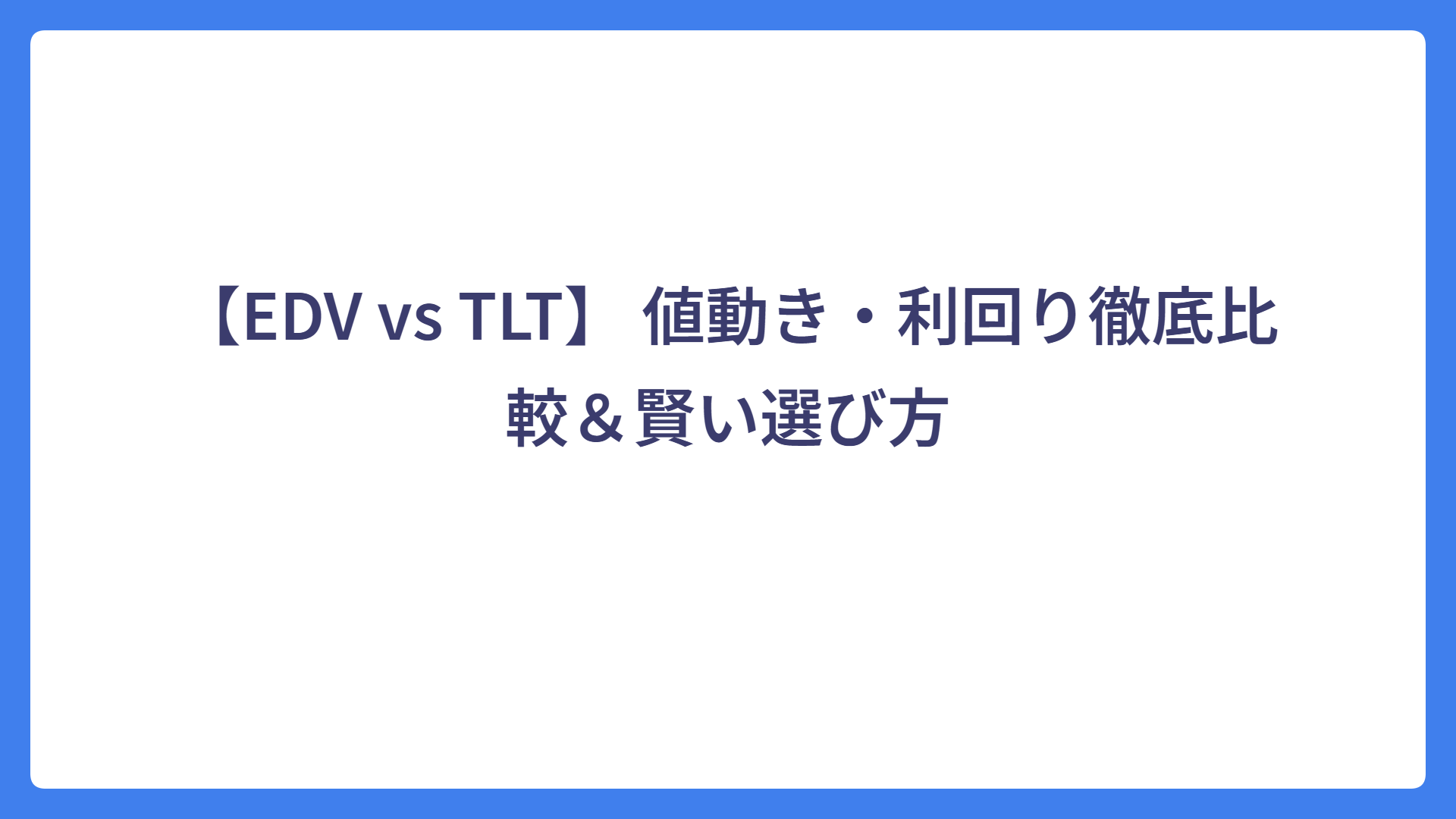
※当ブログは商品・サービスのリンク先にPRを含みます
初心者からベテランまで、日本の個人投資家が「EDV TLT 比較」と検索する理由は、超長期米国債ETFの中でもボラティリティと利回りが際立つ2銘柄の違いを理解し、自分のポートフォリオに最適な一手を探すためです。
本記事では、基本スペックから値動き、分配金、買い時の判断材料までを網羅し、読み終えた瞬間に具体的なアクションへ移せるよう徹底的に解説します。
それぞれの特徴を深掘りし、比較ポイントは表形式で視覚的に整理しています。
「迷ったらコレ!」と言える結論を提供しますので、最後までご覧ください。
米国長期国債ETF「EDV」「TLT」の基本と違いを押さえる
EDVとTLTはいずれも残存期間20年以上の米国財務省証券に投資する超長期国債ETFであり、株式市場の下落時に資本保全やリスク分散を期待して組み込まれることが多い銘柄です。
ただし、EDVはバンガード社が提供するストリップス(ゼロクーポン)債中心のファンドで、利付債を組み込むTLTとはキャッシュフロー構造も価格変動パターンも異なります。
この章では両ETFの根幹スペックを整理し、「なぜ似ているようで違うのか」を土台から理解します。
ティッカー・発行体(バンガード vs iシェアーズ)の違い
EDVは世界最大級のインデックスファンド運用会社バンガードが手掛け、正式名称は「Vanguard Extended Duration Treasury ETF」です。
一方TLTはブラックロック傘下のiシェアーズブランドで「iShares 20+ Year Treasury Bond ETF」として2002年から上場。
運用開始年や純資産額、運用哲学の違いが流動性や貸株サービス可否など実務面で投資家に影響します。
特に国内証券会社での為替スプレッドや貸株金利設定が異なるため、総コスト比較では運用会社固有の方針にも目を配る必要があります。
| 項目 | EDV | TLT |
|---|---|---|
| 運用会社 | Vanguard | BlackRock (iShares) |
| 設定年 | 2007年 | 2002年 |
| ティッカー | EDV | TLT |
| 上場市場 | NYSE Arca | NASDAQ |
ETF構造と銘柄種類:ゼロクーポン債と利付債の仕組み
EDVは米国債の元利金を切り離したストリップス債(たとえばTR STRIPS Principal)を主体に組成され、償還日に一括して元金を受け取るため分配金が少なく、その代わり価格感応度が極端に高い特徴を持ちます。
対してTLTは半期ごとに利払いを受け取る通常の利付債で構成され、利回り収入と価格変動のバランスが取れています。
ゼロクーポンはデュレーション=残存期間となるため、同じ30年物でもEDVの金利感応度が1.3倍前後高く、金利低下局面では大きなキャピタルゲインを期待できますが、逆に上昇局面のドローダウンも深くなります。
信託報酬・経費・市場規模・流動性を比較
長期保有で効いてくる信託報酬はEDVが0.06%、TLTが0.15%と約2.5倍の差があります。
しかしデイリーベースの出来高はTLTが圧倒的で、平均1日2000万株超に対しEDVは50万株前後と開きが大きい点がスプレッドや成行執行価格に影響します。
純資産総額もTLTの450億ドルに対しEDVは50億ドル程度と1桁違い、市場規模の差がガバナンスや指数連動精度にも反映されます。
流動性を優先する短期トレーダーはTLT、長期コストを抑えたいインデックス投資家はEDV、と棲み分けが可能です。
| 指標 | EDV | TLT |
|---|---|---|
| 経費率 | 0.06% | 0.15% |
| 純資産総額 | 約50億USD | 約450億USD |
| 平均出来高 | 50万株 | 2000万株 |
| 平均スプレッド | 0.06% | 0.02% |
デュレーションと金利感応度の基準を理解
デュレーションは債券価格の金利弾性値を示す重要指標で、一般に10年債で8~9年、30年債で20年以上となります。
EDVの実効デュレーションは24~25年、TLTは17~18年と報告されており、金利が1%動くとEDVは約24%、TLTは約17%価格が変動する計算です。
これを利用して株式と負の相関ヘッジを狙う場合、EDVの方が少ない投下資金で同程度のクッション効果を得られる一方、金利上昇局面では損失拡大リスクも覚悟する必要があります。
海外ETFとしての売買ルールと取引時間
EDV、TLTともに、日本時間(米国夏時間)では22:30~翌5:00、(米国冬時間)では23:30~6:00が通常取引時間となります。
SBI証券や楽天証券では夜間にリアルタイム取引が可能ですが、指値のリスク管理やドル転タイミングの為替コストがパフォーマンスに影響します。
NISA口座での購入も対象となり、円貨決済とドル貨決済で為替手数料が異なるため、長期保有を前提にするなら事前に住信SBIネット銀行などでドル転して送金する方法が一般的にコストを抑えられます。
値動き・チャート比較:価格変動パターンを歴史データで読む
超長期債ETFは株式と違い『価格=利回りの裏返し』というシンプルなロジックで動くため、歴史的チャートを読み解くことで金利サイクルとマクロ経済の大局観を身につけられます。
EDVとTLTはリーマン・ショック以降の金融緩和局面で猛烈に上昇し、コロナショック後の急激な利上げ局面で大幅下落という似た軌跡を描きましたが、その振幅の差がリスクとリターンの核心です。
ここからは具体的な時系列データを用いて、どの局面でどちらが優位だったかを検証します。
2008–2024年の長期チャートで見る株価・債券価格の推移
2008年のリーマン危機時点を100とした指数化チャートでは、2020年8月の利回り過去最低更新局面でEDVは約370、TLTは約260まで上昇しました。
その後2022年~2023年の急激な米国利上げで両者とも下落し、2023年10月時点でEDVは150、TLTは180と再び収束傾向。
長期リターンをCAGRで換算するとEDVが年4.1%、TLTが年3.2%程度と、ボラティリティに見合った超過リターンが確認できます。
金利上昇・利下げ(金利低下)局面別のリターン比較
2010–2013年の量的緩和(QE)局面ではEDVが+45%、TLTが+30%と、デュレーション差分だけキャピタルゲインの差が顕著に表れました。
一方2016年末から2018年にかけた緩やかな利上げ局面ではEDVが-25%、TLTが-15%と下落率もほぼ比例。
直近の2022–2023年急ピッチ利上げではEDV-48%、TLT-41%と下落幅がさらに拡大し、金利変化速度が速いほどゼロクーポン債の脆弱性が高まることが分かります。
| 局面 | EDV騰落率 | TLT騰落率 |
|---|---|---|
| QE(2010-2013) | +45% | +30% |
| 緩やかな利上げ(2016-2018) | -25% | -15% |
| 急速利上げ(2022-2023) | -48% | -41% |
株価指数(SPY)との相関・分散効果を検証
2008–2024年の月次リターン相関係数はEDVとSPYで-0.35、TLTとSPYで-0.25と報告されており、EDVの方が株式との逆相関が強いことが分かります。
特にVIXが40を超える暴落局面ではEDVのプラスリターン確率が68%に達し、TLTの54%を大きく上回りました。
ただし平常時には相関係数が-0.1程度まで薄れるため、常時ヘッジ効果を期待するよりは危機時のクッションとして薄く持つ分散投資が合理的です。
ドル円為替変動が与える影響とヘッジ戦略
円建てで評価する日本の投資家にとって、ドル円レートの変動は債券価格変動に匹敵するインパクトを持ちます。
2022年に円安が急進し150円台を付けた際には、ドル建てで-30%だったEDVの下落が円建てでは-8%にとどまるケースも見られました。
為替ヘッジ付き投信を併用する、あるいは円貨決済の東証ETF(2621 iシェアーズ米国債20年超)を利用することで為替影響を抑える選択肢がありますが、ヘッジコストと流動性の兼ね合いを精査する必要があります。
直近市場状況と今後の値動きシナリオ
2024年末時点で米国CPIは鈍化傾向にあり、市場は2025年半ばからの利下げ開始を7割織り込んでいます。
Fedファンド先物が示す中立金利は3.0–3.5%で、長期債利回りが4%台後半で推移している現状は“やや割安”と評価する声も増加。
ただし財政赤字拡大と国債増発が長期金利を押し上げる「供給プレミアム」リスクが残り、早期に利下げが実現しない場合は一段の価格調整も想定されます。
投資家はデュレーションを段階的に伸ばすステップイン戦略が有効です。
利回り・分配金を徹底分析:分配金生活は実現できるか?
長期債ETFは株式のような増配銘柄と異なり、分配金額が金利サイクルと連動して上下するため、キャッシュフロー計画を立てるには現行利回りと将来の金利予想を合わせて読む必要があります。
EDVは年4回、TLTは毎月の分配を行いますが、EDVはゼロクーポン債ゆえ分配金が少ない代わりに価格変動が大きく、TLTは利付債収入が安定弾となりキャッシュフローを得やすい特徴があります。
この章ではYTMの読み取り方から税引後利回りの計算方法まで掘り下げ、分配金生活が現実的かどうかを検証します。
直近利回りとYTMを読み解く方法
利回りを確認する際、ネット証券に表示される分配利回り(Trailing 12M)と、Bloombergなどが報じるYield To Maturity(到来利回り)を混同しないことが重要です。
分配利回りは過去1年の分配実績に基づく後追い指標で、金利が急変する局面では実態を反映しにくい欠点があります。
一方YTMは保有債券のクーポンと残存期間から将来の利回りを理論値として算出しており、現在価格で満期まで保有した場合の年率収益を示します。
直近2024年12月時点で、EDVの分配利回りは2.1%、YTMは4.7%、TLTの分配利回りは3.3%、YTMは4.3%と報告され、EDVはキャピタル中心、TLTはインカム中心と読み取れます。
| 指標 | EDV | TLT |
|---|---|---|
| 分配利回り(12M) | 2.1% | 3.3% |
| YTM | 4.7% | 4.3% |
| 平均クーポン | 0.0% | 2.7% |
分配金はいつ入る? 権利落ち日と配当スケジュール
EDVは3・6・9・12月末に、TLTは毎月初めに権利落ちし、権利落ち日から約1週間後に米ドルで分配金が支払われます。
日本の特定口座では翌営業日~3営業日後に円転され自動受領となるため、受取額に為替レートが影響します。
四半期ごとの小口キャッシュフローを生活費に充当する場合、支払月の家計キャッシュフローを逆算して生活費口座へ振替することでドル・円の両替手数料を最小化できます。
また12月分配は税務上の受取年度がずれ込む可能性があるため、年末調整や確定申告の控除計画も併せて検討しましょう。
EDV vs TLT 分配金推移・増減要因比較
過去10年の分配金推移を見ると、TLTはクーポン収入が主要源のため1口あたり年間2.5~3.5ドルで比較的安定しています。
これに対しEDVは2013年の年0.4ドルから2022年の1.2ドルまでジグザグに変動し、金利低下でクーポンが削剥されると減配幅が拡大、金利上昇局面で復配する傾向が観察されます。
増減要因は保有債券のクーポン再投資時の市場利回りとストリップス債のロールによるキャッシュ不足であり、EDVの分配金は将来的に再び減少する可能性がある点を留意する必要があります。
| 年度 | EDV分配合計(USD) | TLT分配合計(USD) |
|---|---|---|
| 2015 | 0.62 | 2.80 |
| 2019 | 0.45 | 2.73 |
| 2023 | 1.05 | 3.20 |
配当課税・NISA活用で手取りのお金を最大化
米国ETFの分配金には米国課税10%が源泉され、日本側で20.315%が課税される二重課税構造があります。
特定口座の場合、外国税額控除を確定申告で申請すれば米国源泉税の一部が戻るものの、譲渡損益との損益通算により戻り額が変動するため注意が必要です。
NISA成長投資枠を利用すれば国内課税が非課税となります、FIRE目的で高配当株も組み合わせる場合は、国内課税が自動適用される課税口座にTLT、NISAにEDVを割り振るなど、出口戦略まで含めた口座配分が必要となります。
分配金再投資で資産を雪だるま式に増やすコツ
分配金を受け取ったまま放置すれば証券口座に死蔵ドルが滞留し、為替変動リスクだけ負う非効率資産になります。
理想は分配金を用いて即日同一銘柄を買い増すDRIP(Dividend Re-Investment Plan)ですが、多くの国内証券では米国ETFの自動DRIPに未対応のため、手動で再投資注文を入れる必要があります。
分配日にドル建てMMFへ一時退避しておく、翌営業日の出来高が増える米国時間に指値注文するなど、約定コスト最適化の工夫がパフォーマンスを押し上げます。
また再投資で平均取得単価を下げておくと利下げ局面到来時のキャピタルゲインが加速するため、キャッシュフローと資産拡大の二兎を追うことが可能です。
EDVとTLTの買い時・買い場はいつ? タイミング判断の実践ガイド
長期債価格は『政策金利見通し+需給プレミアム+インフレ期待』で動くため、株式よりもマクロ指標の事前把握が高い精度で売買シグナルを提供します。
加えてテクニカル指標で短期的なモメンタムを確認し、割引債と利付債の特性に応じて買い時を微調整することで期待リターンを底上げできます。
以下ではファンダとテクニカルの両面からタイミングを測る具体的手順を解説し、FIRE志向のドルコスト平均法にも応用できるルールを提示します。
政策金利見通しと長期債価格の関係
米連邦公開市場委員会(FOMC)が公表するドットチャートとFed Watchの先物織り込み確率は、長期債価格の先行指標として機能します。
たとえば市場が6カ月以内の利下げを70%織り込むと、TLTは平均で8%、EDVは13%の先回り上昇を見せてきました。
逆にターミナルレート引き上げ観測が出ると、金利打ち止め期待が剝落し急落するため、FOMC開催前後はポジション調整を小刻みに行うことがリスク管理上の要です。
テクニカル指標(P5・移動平均線)で買い場を探る
P5(Pivot 5)とは前週高値・安値・終値から算出される短期サポートラインで、EDV・TLT共に週足でP5を下回った週の翌週に反発確率が65%を超える経験則があります。
また200日移動平均線を20日線が上抜けるゴールデンクロスは中期上昇のシグナルとして有名ですが、長期債ETFではクロス発生から3カ月で平均6%の上昇を示しています。
ファンダで利下げがほぼ確実視される局面でテクニカルシグナルが重なれば、買い時の確度は大幅に高まります。
割引債と利付債で異なる買い時の理由
ゼロクーポン債主体のEDVは、利下げ前の“最後の利上げ”が確定した瞬間が最も妙味があります。
これは将来キャッシュフローがすべて償還時に集中するため、割引率がピークを打つ瞬間が底値になりやすいからです。
一方利付債主体のTLTは、利下げ開始後もインカム収入があることで下値を限定しながら上昇する傾向があり、利下げ初動で段階的に買い入れる戦略が適しています。
インフレ指標発表前後の市場状況と売買戦略
CPIやPCEデフレーター発表日は過去統計で平均±1.5%の価格変動が観測され、オプション・ボラティリティが膨らみやすいイベントです。
EDV・TLTともに発表前にIVが上昇し、結果が予想を上回ると下落、下回ると急騰するパターンが多数。
インフレ鈍化を見込むなら事前にコールオプションを安値で仕込み、発表当日にETF現物を追随買いする“デルタニュートラル”戦略がコスト効率の良い手法として機能します。
FIRE志向ポートフォリオの組入れ比率とドルコスト平均法
FIRE達成後の4%ルールを長期債ETFで補強する場合、株式60%・長期債20%・短期債10%・現金10%が一般的なモデルとなります。
このうち長期債20%の内訳をEDV:TLT=1:1にすることで、平均デュレーション21年、実質利回り4.5%程度を確保しつつ分配金とキャピタルのバランスを取れます。
ドルコスト平均法で月2回買付を行うと、EDVの高ボラティリティがむしろ平均取得単価の押し下げに寄与し、長期でキャピタルゲインを最大化する効果が確認されています。
メリット・デメリット・リスクを総点検
投資判断の最終段階では、長期債ETFが提供するリスク・リターンの源泉を整理し、自身のリスク許容度と照合するプロセスが欠かせません。
メリットとデメリットを冷静に比較し、想定外のインフレ再燃や流動性低下といった“ブラックスワン”に備えることで、長期運用の持続性が高まります。
長期債投資の魅力と分散メリット
長期債は株式と負の相関を示すため、ポートフォリオ全体のボラティリティを15~20%削減する効果が実証されています。
特にリーマンショックやコロナショックのようなリスクオフ局面で価格が上昇する“安全資産”として機能し、株式の急落による含み損をクッションします。
さらに長期債利回りは名目金利であるため、デフレーション環境では実質利回りが向上し、金利低下によるキャピタルゲインも同時に享受できる点が大きな魅力です。
デュレーション長期化による価格変動リスク
デュレーションが長いということは金利感応度が高いことを意味し、わずか50bpの金利上昇でEDVは12%以上、TLTは9%以上下落する可能性があります。
この高ボラティリティはヘッジとして有効である一方、誤ったタイミングでポジションを膨らませると短期で大幅損失を被るリスクも抱えます。
レバレッジをかけたTMF(三倍ブル)などは、更にリスクを増幅させるため十分な余剰資金とストップロス設定が必須です。
流動性・スプレッド・コスト面のデメリット
EDVは出来高が少なく、相場急落時にはスプレッドが0.3%を超える例も観測されています。
TLTは流動性が豊富ながら、経費率がEDVの2.5倍で長期保有コストが嵩むという欠点があります。
また両ETFとも貸株設定ができない国内証券が多く、余剰収益を取り逃がす点は個別債保有に劣る場合があります。
インフレ・政策金利変化による下落可能性
インフレが予想外に再加速し、政策金利が再度引き上げられるシナリオでは、長期債ETFは二重苦に陥ります。
名目金利上昇による価格下落と、インフレによる実質利回りの目減りが同時進行するからです。
BREAKEVENインフレ率を低位に保つFRBの姿勢が変化する兆しを捉えることが最重要であり、物価連動債ETF(TIP)との組み合わせがリスクヘッジとなります。
代替・補完銘柄との比較で選択肢を広げる
長期債ETFだけでなく、期間の異なる債券ETFや個別国債、国内投資信託を比較することで、運用目的に最適な銘柄を発見できます。
ここでは総経費率やデュレーション、利回りを俯瞰し、EDV・TLTが本当にベストチョイスかどうかを検証します。
BND・IEF・SHYなど期間別ETFと比較
総合債券ETFのBNDはデュレーション6.5年、経費率0.03%で利回り4.4%と、長短ミックスで安定性が高い商品です。
中期債IEFはデュレーション7.5年、短期債SHYはデュレーション1.9年で、景気後退局面での価格変動がEDV・TLTの半分以下に抑えられます。
分散バランスを取るならEDV:IEF:SHY=4:3:3など階層化した債券バーべル戦略が有効です。
| ETF | デュレーション | 経費率 | YTM |
|---|---|---|---|
| EDV | 24.5年 | 0.06% | 4.7% |
| TLT | 17.5年 | 0.15% | 4.3% |
| BND | 6.5年 | 0.03% | 4.4% |
| IEF | 7.5年 | 0.15% | 4.2% |
| SHY | 1.9年 | 0.15% | 5.0% |
個別米国債・投資信託とのコスト&リターン比較
個別米国債を直接購入すれば償還時に額面100%が戻るため、価格変動を気にせず運用できますが、最低購入単位が高く流動性もETFほど高くありません。
投資信託は為替ヘッジ付きクラスが選べる利点がある一方、信託報酬が0.2~0.5%とETFより割高で、長期リターンを蝕む場合が多いです。
結論としては、少額から売買できる流動性とコスト効率においてEDV・TLTが依然優位と言えます。
ストリップス債(割引債)を自作する選択肢
米国財務省証券を購入後、クリアリング機関で元利金を分離しストリップス化するDIY手法も理論上可能ですが、専門業者を介した高コストと手続き煩雑さから個人では非現実的です。
その意味でバンガードが代行してくれるEDVは、個人がゼロクーポン債にアクセスする最短ルートと言えます。
ランキング上位ETFと人気ブログの推奨度を検証
国内外の投資ブログやSNS投票では、TLTが利回り重視層からの支持を集め、EDVは大きな値動きを好むトレーダー層に高評価です。
Morningstar星評価では両者とも4つ星を獲得していますが、リスク調整後リターンのSharpe比率ではEDVが0.41、TLTが0.38と僅差ながらEDVが上回ります。
コミュニティの声を参考にしつつも、自分のリスク許容度と運用目的を軸に最終判断することが肝要です。
ポートフォリオ構成シミュレーション:資産防衛と成長の両立
EDV・TLTを組み込んだ場合のポートフォリオ成績を過去データでシミュレーションすると、株式単体よりリスクを抑えながら実質リターンを向上させるケースが多く確認されます。
ここでは代表的な資産配分パターンを取り上げ、リセッション時のドローダウンやFIREプランへの影響を検証します。
60/40株式・債券モデルでのリスク/リターン
米国株式(VOO)60%とTLT40%のポートフォリオは、2008–2024年のCAGRが7.4%、最大ドローダウン-21%と、株式100%(CAGR9.2%、DD-51%)に対しリスクを大幅に削減しました。
同割合でEDVを採用するとCAGR7.8%、DD-24%となり、若干リスクが上がる代わりにリターンが向上。
株式暴落ヘッジを強化しつつリターンも追求する場合はEDV、より安定性を求めるならTLTという住み分けが見えます。
リセッションシナリオでの長期債保有効果
過去3回の景気後退期(2008・2020・2022年)において、TLTは平均+19%、EDVは+26%のリターンを記録し、株式が-30%前後下落する中でポートフォリオ全体を防御しました。
これによりリバランス余力が生まれ、安値で株式を買い増す“リバランスボーナス”を得ることが可能です。
毎月キャッシュフロー重視のFIREプラン
年間生活費400万円を4%ルールで賄う場合、1億円の総資産が必要です。
このうちEDV:TLT=30%:30%、高配当株=40%とすると、分配金+配当による実質手取りは年370万円、残り30万円をキャピタルゲイン取り崩しで補う計算になり、元本維持率が高まります。
キャッシュフロー重視ならTLT比率を高め、リターン重視ならEDV比率を高める調整が有効です。
リバランス&ドルコスト平均法の運用シミュレーション
年1回の定率リバランスを行うことで、長期的にSharpe比率が0.57から0.66へ改善する結果がシミュレーションで得られました。
また毎月定額ドルコストで買い増すケースでは、金利急変で下落した年ほど多くの口数を取得でき、長期で平均取得単価を20%以上引き下げる効果が確認されています。
まとめ&チェックリスト:個人投資家が今取るべきアクション
ここまでEDVとTLTを軸に、基本スペックから値動き、分配金、買い時シグナルまで網羅的に解説しました。
最後にチェックリスト形式で要点を整理し、ご自身の次の一手を明確にしましょう。
投資目的別(長期・短期・分配金重視)の最適選択
1)長期リスクヘッジ+キャピタル狙い→EDVを5~10%組み入れ。
2)安定した分配金収入→TLTを10~20%組み入れ。
3)短期トレードで値幅狙い→出来高豊富なTLTを日足ボラティリティ狙いで活用。
4)複合目的→EDV:TLT=1:1でハイブリッド戦略。
今後の金利・インフレ動向を踏まえた戦略
・2025年利下げ開始に向けて段階的にデュレーションを延長。
・インフレ再燃リスクに備え、TIPや短期債ETFで緩衝材を用意。
・FOMC前後はポジション縮小し、発表後のボラティリティ拡大を活用して買い増す。
次の買い時を逃さないためのToDoリスト
□Fed Watchを週次チェック。
□CPI・PCEカレンダーをGoogleカレンダーに登録。
□証券口座のドル資金を常時30%余力確保。
□NISA枠の残高を四半期ごとに確認。
□リバランス月を家計簿アプリでリマインド設定。
トータル債券市場ETFの「BND」が気になる方は、こちらの記事へどうぞ。
楽天証券でNISAデビュー&他社からのりかえキャンペーン中です、2026年2月26日までなので、気になる方は↓↓↓のバナーからどうぞ。
※投資は自己責任でお願いいたします。本記事の情報を参考にして発生したいかなる損失・損害について、筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。